こんにちは、ばたこです。
- 「1人目の育休中に2人目を授かったら、そのままお休みってできるの?」
- 「3人目が欲しいけど、育児休業給付金ってちゃんともらえるの?」
そんなふうに思ったこと、ありませんか?
 ばたこ
ばたこ育児休業まわりの制度って、複数の法律が関係していて、理解するにはかなり難しいですよね。
私はこれまで社労士事務所で働きながら、労務コンサルタントとして企業の人事担当者や社長さんから
「こういうときどうすればいいの?」とたくさんのご相談を受けてきました。
実はこの育児休業の制度、手続きを行う会社側もよく悩んでいるテーマなんです。
だからこそ、「なんだか難しい…」と感じてしまうのも無理はありません。
この記事では、「産休・育休を連続で取得する方法」と、
「育児休業給付金をもらいながら安心して休むためのポイント」を、
なるべくわかりやすくお伝えしていきますね!
この記事を読んでわかること
- 産休・育休って本当に連続で取れるの?
- 連続で育休を取った場合、育児休業給付金はどうなるの?
- 給付金がもらえなくなるケースと、その対策方法って?
- ちょっと得する!賢い連続取得のコツとは?
産休・育休って本当に連続で取れるの?
結論:連続で取れます!
取得が可能なケースですが以下のとおりです。
- 1人目から2人目の連続取得(※確実に取得可)
- さらに、1人目から2人目まで連続して育休を取得し、その後3人目も続けて取得(※要注意)
これまで労務コンサルタントとして、たくさんのご相談を受けてきましたが、
1人目の育休中に2人目の妊娠が分かって、そのまま復帰せず産休に入る方も少なくありません。
でも中には、「こんなに続けて休んでしまって、会社に迷惑かけてないかな…」と気にして、
退職を考えてしまう方もいらっしゃいました。



でも、そんなに心配しなくても大丈夫です。
次の章で説明します!
従業員が産休・育休を連続で取得したときの会社側の対応
会社としても、産休や育休の間は代わりの方を採用していることが多いので、
あなたが連続でお休みを取っても、その方の契約を延長するなど、しっかり対応してくれるケースがほとんどです。
だからこそ、遠慮せずに自分と家族のタイミングを大切にしてほしいと思います。
連続で育休を取ったら、復帰できなくなる心配はないの?
大丈夫です。
復帰できなくなることは基本的にありません。
理由は、育休から復帰する際は、会社には「原則として同じ仕事に戻す義務」があるからです。
「仕事がなくなっているかも…」といった不安を感じる必要はありません。
さらに、復帰後も育児と両立しやすいような時短勤務や残業免除などの制度があります。
このあたりは、別の記事でくわしく紹介していますので、よければそちらも参考にしてみてくださいね◎
連続で育休を取ると、育児休業給付金はどうなるの?
- 1人目から2人目の連続取得(1人目と同じ額がもらえる)
- さらに、1人目から2人目まで連続して育休を取得し、その後3人目も続けて取得(※要注意)
解説します。
1人目から2人目の育休を連続して取る場合、基本的には1人目のときと同じ金額の給付金を受けることができます。
ただし、さらに、1人目から2人目まで連続して育休を取得し、その後3人目も続けて取得では、
取得の仕方によっては育児休業給付金の対象外になってしまうこともあるので注意が必要です。
どうして給付金がもらえないケースがあるの?
これは「育児休業給付金」の支給ルールが関係しています。
解説しますね。
育児休業給付金を受けるための条件
- 育休に入る前の2年間のうちに、11日以上働いた月が12ヶ月以上あること
(または、1ヶ月80時間以上働いた月でもOK) - 条件を満たせない場合でも、
最長で4年間までさかのぼってカウントしてOKという特例があります。
この要件に該当すれば誰でも育児期間中の給付金が受けられますが、
要注意のケースについては次の章で説明します!
1人目から2人目まで連続して育休を取得し、その後3人目も続けて取得注意!
さきほどの支給ルールに当てはめると、
3人目の育休に入る前の4年間のうちに「働いた月が12ヶ月以上」必要です。
つまり、1人目→2人目と連続で育休を取っていた場合、働いた実績が足りなくなることがあるんです。
イメージで見ると…
- 1人目の育児休業を2年間取得
- その後、2人目の育児休業も2年間取得
この場合、3人目の休業に入る前の4年間はすべて「育休中」となるため、
さかのぼっても“働いた実績がゼロ”という状態になります。



育児休業の期間中に給付金を検討している人は、この点が一番注意すべきポイントです。
このようなケースでは、育児休業給付金がもらえない可能性があるため、
早めに確認して、必要であれば復帰をはさむなどの対策がとても大切です。
給付金の条件に“足りない”かも…というときの対策
「あと数ヶ月だけ働いた実績があれば給付金がもらえるのに…」
そんなときは、次のような対策があります。
1:起算日を見直す
休業前の2年間(4年間)ルールですが、原則は育児休業を開始する前ですが、
産前休業開始前を起算日にできる特例があります。
就労実績がギリギリ足りない場合などは、この特例を使うことで12ヶ月を満たせるケースがあります。
図でイメージすると…
| 起点 | 内容 |
|---|---|
| 育休開始前 | 育休の直前が「産後休業」なので、休業期間が2年の中に入ってしまう |
| 産前休業開始前 | 実際に働いていた時期からカウントできるようになる(勤務実績が増える) |
2:一度職場に復帰して、働いた月数を増やす
たとえば、育休明けに一度復帰して、11日以上働くと「1ヶ月分」としてカウントされます。
(※11日未満でも、80時間以上働いていればOKです)
この実績が1ヶ月分に加算されることで、
育児休業給付金の支給条件をクリアできる可能性が高くなります。
さらにうれしいポイントとして、
有給休暇を使って出勤扱いにする方法でもカウント対象になります◎
3:人事や総務に事前に確認しておく
あと何ヶ月分の実績が必要なのか、自分では分かりづらいこともあります。
事前に会社の人事・総務に確認しておくことで、安心してスケジュールを立てることができますよ。
4:会社の対応が不安なときは、自分で確認してみよう!
- 「会社の人事があまり詳しくなさそうで不安…」
- 「ちゃんと条件を満たしてるか、はっきりさせたい!」
そんなときは、自分でハローワークに確認するのもおすすめです。
最寄りのハローワークの窓口で、
これまでの育児休業の取得期間や勤務状況を伝えることで、
育児休業給付金の支給要件を満たしているかどうかを確認してもらえます◎
窓口で伝えるときに持っていきたいもの
- 過去4年間の勤務実績(簡単なメモでOK)
→ 「○年○月~○月は出勤していた」
→ 「月11日以上働いたかどうか」が分かれば◎ - 1人目・2人目の産前休業開始日/育児休業終了日
→ 育休の連続取得をしていた場合は、特に大事な情報です!
得する!賢い連続取得のコツとは?
実は、育休を取るタイミングや制度の使い方を少し工夫するだけで、もらえるお金に差が出ることがあります。
ポイントは「育児休業給付金」と「出産手当金」の違いに注目!
- 育児休業給付金(雇用保険から支給)
→ 最初の180日間は67%、181日目以降は50%の支給率に下がります。 - 出産手当金(健康保険から支給)
→ 産前産後休業中に約67%の手当がもらえます(しかも途中で下がらない!)
どっちが得なの?
もし「育休を長く取るより、早めに産前休業に入れる状況」であれば、
出産手当金を優先的に受けた方が支給率的にはお得なケースもあります。
たとえば…
1人目の育休中に2人目の妊娠が分かり、育休を途中で終了して産前休業に入る場合
→ 育児休業給付金(50%)より、出産手当金(67%)に切り替えた方が支給率が高い!
まとめ:こんな人はチェック!
| 状況 | おすすめの工夫 |
| 育休が181日を超えている ※(産前42日のタイミングなら) | → 産前休業(出産手当金)に早めに切り替えた方が得かも |
| 連続して休業中&次の妊娠が分かった ※(産前42日のタイミングなら) | → 育休を早めに終えて産前に切り替える選択肢も◎ |
「制度は複雑だけど、ちょっとした工夫で損しない」って大事ですよね。
わかりにくいところは、私ばたこがかみ砕いて解説しますので、気になる方はお気軽に聞いてくださいね◎



出産手当金には、入金まで少し時間がかかるという点があります。
すぐに受け取れないこともありますが、
私は「少しでも多くもらえる方がメリットがある」と思います。
まとめ|産休・育休を連続で取得するときのポイント
産休・育休は連続して取得することができます。
でも、給付金をもらえるかどうかにはルールがあるので、事前の確認とちょっとした工夫が大切です。
この記事のポイントまとめ
- 産休・育休は連続取得OK!
→ 1人目から2人目へ、復帰せずにそのまま休むことも可能です。 - 会社の対応が不安でも心配しすぎなくて大丈夫
→ 代替人員で対応していることが多く、安心して休めます。復帰後は元の業務に戻るのが基本です。 - 育児休業給付金には“12ヶ月の就労実績”が必要
→ 育休が続くと勤務月数が足りず、3人目のときに給付金が出ないことも。 - 起算日は「育休開始前」or「産前休業開始前」から選べる特例あり
→ 実績がギリギリのときは、「産前休業前」からカウントした方が有利になるケースも。 - ハローワークでも確認可能!
→ 実績に不安があるときは、自分で調べて確かめるのも◎ - 給付金はタイミングによって“もらい方”に差が出る!
→ 出産手当金(67%)と育児休業給付金(50%)の切り替えを意識すると“ちょっと得”できます。



「こんなに休んで大丈夫かな…」
「この制度、なんだか難しい…」
そんな場合な気軽にコメントくださいね。

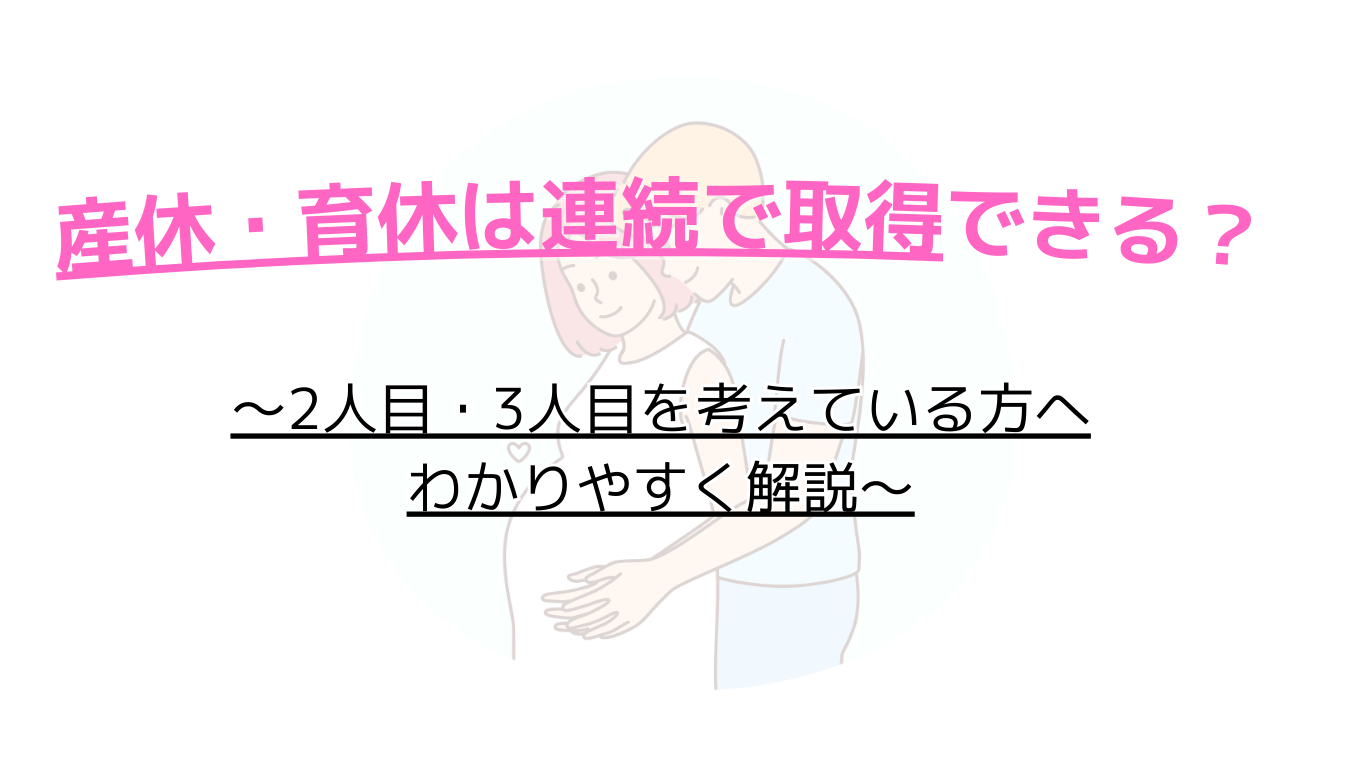
コメント