こんにちは。ばたこです。
今回は、男性が育休を取得したいときに知っておくべきことをまとめました。
- 「会社にどう切り出せばいいか分からない」
- 「上司に反対されたらどうしよう」
そんな不安を抱えている方に向けて、
会話スクリプトもコピペOKで用意しています。
この記事を読めば、
- 男性育休の最新ルール
- 会社への上手な伝え方
- トラブル時の対処法
- 事前に準備しておくべきポイント
こういったことが、理解できると思います。
育休は、法的に認められた権利ですので、未来の家族のために、今から準備していきましょう!
第1章|男性育休はいつから取得できる?【産後パパ育休も解説】
育休って、実はかなり自由度が高い制度になってきています。
特に2025年の法改正で、男性も取りやすくなったんです。
まずは基本をおさえましょう。
育児休業と産後パパ育休の違いとは?
ざっくり説明すると、こんな感じです。
| 制度名 | 取得できる時期 | ポイント |
|---|---|---|
| 育児休業 | 子どもが1歳になるまで(条件によって最長2歳まで) | 男女OK。従来からある育休制度。 |
| 産後パパ育休 | 出生後8週間以内に最大4週間取得できる | 特に男性向けに新設された、柔軟な休業制度。 |
「産後パパ育休」は、普通の育休とは別枠で取れます。
つまり、産後パパ育休→通常の育児休業と、連続して使えるわけです。
産後パパ育休はこう使える【ポイントまとめ】
- 出産後8週間以内に4週間まで取得できる
- 2回に分けて取ることもできる
- 育児休業とは別に取得できる
- 休業中でも最大10日間は働ける(労使合意があれば)
さらに、2025年4月からは、給付金が手取り10割相当まで引き上げられました。←(※第1章で触れてる法改正により新設された部分はここです)
つまり、
「育休=給料が減って不安」
というハードルも、ぐっと下がったということです。
 ばたこ
ばたこ「取れるなら取りたい。でも、迷惑かけそうで言い出せない…」
そんなふうに感じるかもしれません。
でも育休は、あなたと家族のための正当な権利です。
自信を持って、取得を検討していきましょうね!
第2章|会社に育休を伝えるときのコツ【失敗しない話し方】
育休を取りたいと思ったら、
まずやるべきことは「伝え方」を準備することです。
いきなり「育休取ります!」はNG。
ちゃんと順番を踏んで話すことで、スムーズに理解を得られます。
伝えるときの5ステップ
会社への伝え方は、ざっくり次の流れがおすすめです。
| ステップ | 内容 |
|---|---|
| ① 相談のアポを取る | まずは「相談したいことがある」と声をかける |
| ② パートナーの出産予定を伝える | 「◯月に出産予定です」と状況を説明 |
| ③ 育休を取得したい意向を伝える | 取得希望時期・期間もできるだけ伝える |
| ④ 引き継ぎや業務整理の意向を伝える | 「迷惑をかけないよう調整したい」と協力姿勢を見せる |
| ⑤ 今後の社内手続きについて確認する | 「私から総務に連絡しますか?それとも上司からでしょうか?」と聞く |
この5ステップを押さえておけば、大きなトラブルにはなりません。
【コピペOK】直属の上司に伝えるトークスクリプト
育休を伝えるとき、こんな感じで話すとスマートです。
👤本人(あなた)
「お疲れさまです。少しご相談したいことがありまして、
短時間で構いませんので、お時間いただけますでしょうか?」
(アポ取りOK後)
「実は、パートナーが◯月に出産予定となりまして、
私自身も育児にしっかり関わりたいと考えています。
そこで、育児休業を取得させていただきたいと思い、
まずはご相談に伺いました。
できるだけ業務に支障が出ないよう、引き継ぎなども早めに準備していきたいと考えています。
今後の手続きについて、私から総務に連絡する形でしょうか?
それとも、上司から総務へ連携していただく形になりますでしょうか?」
こんなふうに、相談モードで進めるのがコツです。
押しつけるような言い方にならないので、上司も受け止めやすくなりますよ。



最初から「取るか・取らないか」じゃなくて、
まずは「相談」からスタートすると、驚くほど話が進みやすくなります。
「味方を作る」イメージで動いてみましょう!
また、出産後に伝えるのではなく、妊娠時期から伝えるのがミソです!
第3章|もし会社がいい顔をしなかったら?【交渉術と事前準備】
理想は「いいですね、応援します!」だけど、
現実には、そううまくいかないこともあります。
でも安心してください。
育休は法律で守られている権利です。
ちゃんと事前に準備しておけば、慌てる必要なしですよ。
法律で守られていることを知ろう
育児休業は、
「取得させない」「不利益な扱いをする」こと自体が法律違反です。
法律でバッチリ守られているので、
「うちは男は取らないから」みたいな理由は通りません。
もしも圧力をかけられたり、イヤミを言われたりしたら、
その時点でハラスメントに該当する可能性もあります。
まずは、自分が守られていることを知っておきましょう。
ただし、なかには取得できない人もいます。
それは別の記事で紹介していますので、詳しく知りたい方はこちらからご参照ください。
事前に“味方”を探しておく
会社によっては、直属の上司よりも
- 総務
- 人事部
- コンプライアンス窓口
- ハラスメント対応窓口
こういったところが制度に詳しい場合もあります。
育休の取得相談をするときは、
あらかじめ「制度に詳しい部署」を味方につけておくと安心です。
ポイントは、
「上司との面談前に軽く情報収集しておく」こと。
- 「社内には育休の相談窓口がある」
- 「育休を取った人が過去にいるか確認する」
これだけでも、心の支えになりますよ。
上司と話すときは「確認する」スタイルで
もし反対されたり、はぐらかされた場合は、
言い返すんじゃなくて、あくまで確認という形で進めましょう。
👤本人(あなた)
「念のためご確認させていただきたいのですが、
育児休業を希望する場合、社内ではどのような手続きが必要でしょうか?」
こうすると、
- 会社を責めてる感じがゼロ
- 上司も「じゃあ手続き確認しようか」と自然に動きやすい
- 対立せず、相談ベースで進められる
というメリットがあります!



対立する必要なんてありません。
“粛々と進める”ことが、一番強い交渉術ですよ。
それでも難しい場合は、外部相談を
どうしても社内でうまくいかないときは、
外部の専門機関に相談することもできます。
- 社内・社外ハラスメント窓口 ←ほとんどの会社が設置されていると思います。
▼設置されていない場合 - 労働局の「雇用環境・均等部(室)」
- ハローワーク
- 法テラス
- 弁護士事務所
これらの窓口は、無料で相談できることも多いです。
無理に自分ひとりで抱え込まないで、
「ちゃんと相談できる場所がある」ことを覚えておいてくださいね。
第4章|育休を取得する前にやっておくと安心なこと【未来の自分のために】
育休を取得することは、
あなたにとっても、会社にとっても大きな出来事です。
「休みに入ったらあとはお任せ!」ではなく、
事前にできる準備をしておくと、安心感がまったく違います。
育休に入る前にやっておきたいこと
まず、こんなことを整理しておきましょう。
| やること | ポイント |
|---|---|
| 上司との調整 | どの業務を、どんなスケジュールで、どう引き継ぐか。 あらかじめ自分なりのプランを考えておくと、話がスムーズになりますよ。 |
| 業務の棚卸し | 自分の担当業務を書き出してリスト化 |
| 引き継ぎ資料の作成 | 誰が見てもわかるようにマニュアルを作る (※現場をあける期間に応じ完成度を上司に相談するのがベストです) |
| チーム内の共有 | 引き継ぎ資料の読み合わせや実際に業務に取り組んでもらい不明点を休業する前に解決しましょう。 |
| 育休中の連絡ルールを決める | 連絡を取るかどうか、どのツールを使うか |
こうしておくと、育休に入った後も、
「あれ、どうだったっけ?」と連絡が来るリスクがぐっと減ります。
育休中の収入・給付金を確認しておく
育休中は、育児休業給付金が支給されます。
そして2025年からは、
条件を満たせば「手取り10割相当」まで給付金が増えました。
- 最初の28日間は手取り10割に近い給付
- 社会保険料も免除
- 給付金は非課税
つまり、
手取り10割相当期間後は、思っているより収入減少は少ないということ。
収入のシミュレーションをしておくと、
「育休中どうしよう…」という不安もかなり減りますよ。
育休明けの働き方もイメージしておく
育休は、いつか必ず「明ける日」がきます。
そのときに、
- 育休中も、自分の仕事に関する情報は、できる範囲でキャッチしておく。
- 産後パパ育休は2回、育休も2回まで分割取得できる制度です。
もし残りがあるなら、「もう一度取るか?」検討する - これまでと同じ働き方で、家族との時間をちゃんと大切にできるか?
など、ざっくりでもいいのでイメージしておくとスムーズです。
育休中に家族との話し合いを重ねるのもおすすめです。



育休を取るのは「休むため」だけじゃなく、
「家族と向き合うため」の時間です。
そのためにも、仕事をすっきり整理して、
気持ちよく新しいスタートを切りましょう!
まとめ
ここまで読んでくださって、本当にありがとうございます。
男性の育休取得は、まだまだ「前例がない」「勇気がいる」と感じる場面もあるかもしれません。
でも、あなたが一歩踏み出すことは、これからの働き方や家族との時間を変える大きなきっかけになります。
育休は、ただの休みじゃありません。
家族と過ごすかけがえのない時間を作るための、大切な選択肢です。
迷ったらこの記事を思い出して、
「自分にも選ぶ権利がある」ことを、忘れないでくださいね。
今日からできること
- 取得時期や手続きを、軽く調べてみる
- パートナーと今後の働き方について話してみる
- 育休に向けて、業務整理を始めてみる
今できることから、少しずつはじめていきましょう。



男性育休を取るという選択は、
あなた自身だけじゃなく、家族にも社会にも、大きな希望をもたらします。
私も、労務コンサルタントとして多くの企業を見てきましたが、
最初の一人が勇気を出してくれたことで、
「次の人が取りやすくなった」そんな職場もたくさんあります。
あなたの一歩が、きっと誰かの励みにもなります。
応援しています。

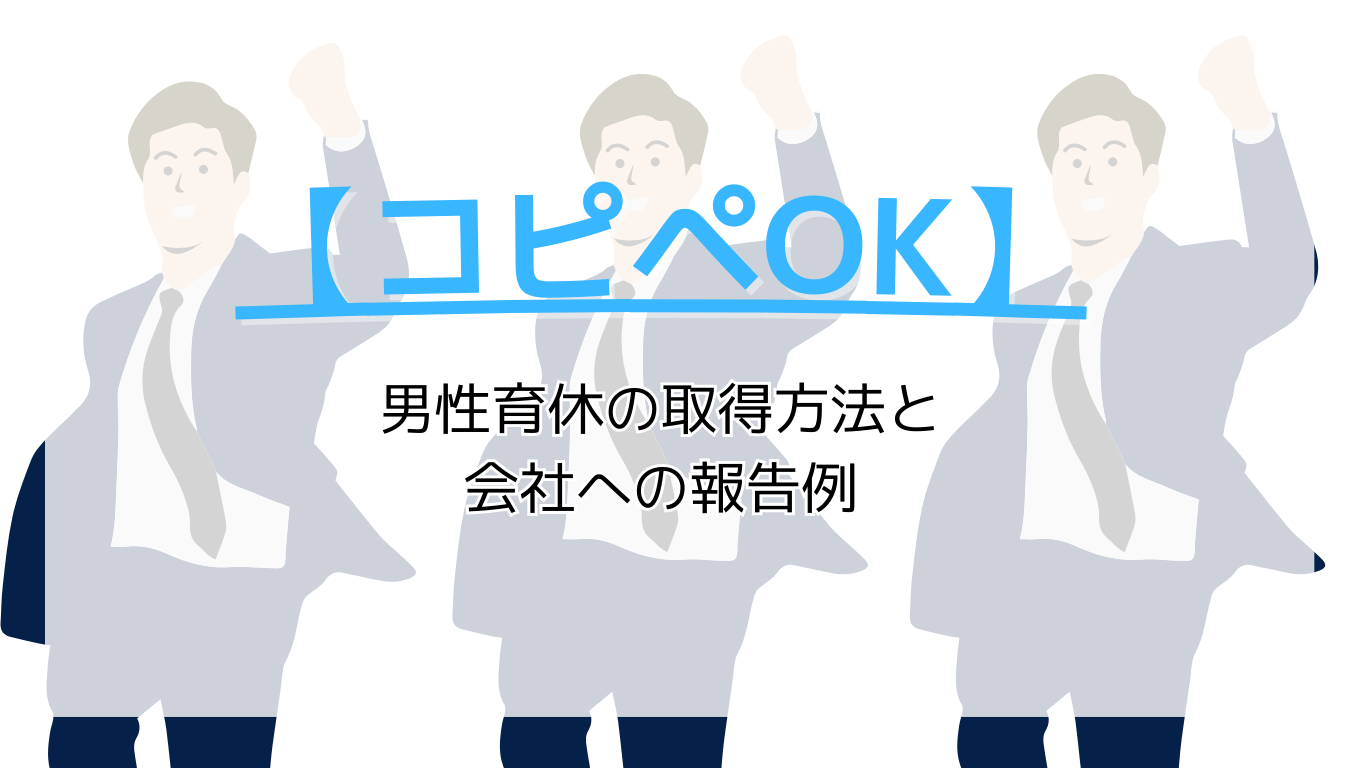
コメント