こんにちは。ばたこです。
「育休=ママが取るもの」そんなイメージ、もう古いかもしれません。
最近では、パパの育休取得も増えていて、制度をうまく使えば「手取りが減らない」どころか、「得する」ケースもあるんです。
この記事では、パパが育休を取ることで得られる経済的メリットや、
2025年から始まった新しい給付制度について、できるだけわかりやすくまとめています。
夫婦で読んで「うちもやってみようかな」と思ってもらえる内容にしているので、ぜひ一緒に読んでみてください。
1. 育休中は社会保険料が免除される!
育休を取ると、健康保険や厚生年金の「保険料」が免除されます。
しかも、払っていなくても「払ったこととして扱われる」ので、将来の年金額が減ることもありません。
免除の条件は?
- その月の末日に育休を取っている
- もしくは、14日以上連続で育休を取っている
どちらかを満たせば、その月の保険料が丸ごと免除されます。
OKな取得例
- 4月1日から4月30日までまるごと育休 → OK(末日を含む)
- 4月10日から4月24日まで育休(15日間)→ OK(14日以上連続)
- 4月30日から5月15日まで連続育休 → OK(14日以上連続かつ月末を含む)※4月分のみ免除
- 分割した場合も同月内で14日以上あればOK
以下のように、免除対象月がひと目でわかる早見表もチェックしてみてください。
| 育休期間 | 14日以上? | 月末含む? | 4月の保険料 | 5月の保険料 |
|---|---|---|---|---|
| 4/1〜4/30 | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ― |
| 4/10〜4/24 | ⚪︎ | × | ⚪︎ | ― |
| 4/30〜5/15 | ⚪︎ | ⚪︎(4月) | ⚪︎ | × |
| 4/1〜5/31 | ⚪︎ | ⚪︎(両月) | ⚪︎ | ⚪︎ |
NGな取得例
- 4月10日から4月20日まで(11日間) → NG(14日未満)
- 4月1日から4月15日まで育休 → NG(月末を含まない)
どれくらいお得になる?
会社員で年収500万円くらいの人なら、1か月あたり約5〜7万円くらいの負担が減ることも!
 ばたこ
ばたこちょっとした育休のタイミングで、こんなに保険料が減るなんて!知らなきゃ損する制度、ぜひチェックしてね。
2. 育休中に賞与があるときも保険料が免除に?
「育休中にボーナスが出るけど、社会保険料はどうなるの?」
そんなときも、ある条件を満たせば、その賞与にかかる保険料も免除されます。
賞与の免除に必要な条件は?
- 育休を “1か月以上連続して” 取得していること(14日以上では不十分)
- その “賞与の支給月の初日から末日まで” 継続して育休を取得している必要があります。
例えば
- 6月に賞与が出る場合 → 6月1日〜6月30日まで育休を取っていればOK
- 6月1日〜6月14日など “14日間のみ” の育休 → NG(賞与に保険料がかかります)
この免除を使えば、ボーナスの手取りもかなり多くなる可能性があります。
以下は、全国健康保険協会(協会けんぽ)のQ&Aからの引用です:
Q:育児休業中に賞与が支給された場合、健康保険・厚生年金保険の保険料は免除されますか?
A:賞与の支給月において、育児休業等を1か月を超えて取得している場合に限り、保険料が免除されます。
出典:https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3160/r150/
※このルールは、全国健康保険協会(協会けんぽ)のQ&Aなどでも明記されており、賞与に係る保険料の免除は「1か月以上の育児休業」が必要です。 出典:https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3160/r150/



賞与のときは“1か月まるっと育休”がカギ。月初〜月末を意識するだけで、手取りがグッと変わるかも!
3. 2025年からの新制度「出生後休業支援給付金」って?
2025年4月から、パパママ両方が育休を取ると、さらに手取りが増える制度がスタートしました。
どんな制度?
- 夫婦それぞれが「14日以上」の育休を取得する
- この条件を満たせば、67%の育休給付金に加え、13%の「出生後休業支援給付」が加算される
合計80%の給付ですが、これは「非課税」で、かつ「社会保険料も免除」なので……
➡ 実質の手取りは、休業前とほとんど変わらない=手取り10割に近い!
モデルケースでの比較(既婚・子1人・年収500万円)
| 項目 | 通常勤務(月額) | 育休中(給付金) |
|---|---|---|
| 基本給 | 300,000円 | — |
| 役職手当 | 50,000円 | — |
| 総支給額 | 350,000円 | 約261,333円(非課税) |
| 健康保険料 | -17,000円 | 0円 |
| 厚生年金保険料 | -32,000円 | 0円 |
| 雇用保険料 | -1,050円 | 0円 |
| 所得税 | -3,000円 | 0円 |
| 住民税 | -10,000円 | 0円 |
| 手取り額 | 287,950円 | 約261,333円 |
※育休中の給付金は非課税かつ保険料免除のため、
実質的に通常勤務時の手取りとほぼ変わらない水準になります。



補足部分が専門的になってしまうのですが、
具体的な計算方法は以下のとおりです。
補足:支給額は「月収の80%」ではなく、日額換算で算出されます。
【計算式】
- 月給35万円の場合 → 支給基礎日額は(35万円 × 6ヶ月)÷ 180日 = 約11,667円/日
- その80% × 28日分 = 約261,333円
が、出生後休業支援給付金を含めた最初の支給額となります。(28日分の上乗せ分)
育休開始から30日間で比較する場合
- 残り2日間 × 67%支給 = 約15,620円 合計 約276,953円(※非課税・保険料免除)
- 通常勤務時の手取り額(約286,950円)との差は約1万円です。
- 差額の割合で見ると、276,953円 ÷ 286,950円 ≒ 約96.5%
つまり、“約10割に近い”とはいえ、実際は手取りベースで約3.5%減になります。
注意点:この“手取り10割”はずっと続くわけではない!
- この手取り10割に近い状態は、「育休取得開始から28日間限定」です。
- その後は以下のように給付率が変わります。
| 育休期間 | 給付率(手取り換算) |
|---|---|
| 1日目〜28日目 | 67%+13%(=80%) |
| 29日目〜180日目(約6ヶ月) | 67%(育児休業給付金) |
| 181日目以降 | 50%(育児休業給付金) |
非課税・保険料免除の効果も含めると、67%でも手取りは7〜8割程度になりますが、
「最初の1ヶ月が特にお得」という点を知っておくと育休のスケジュールも組みやすくなります。



“手取り10割”って言葉に驚いたけど、実は28日間限定。でもタイミング次第でここまで得できるの、すごい。
4. 育休ってどう取る?夫婦で考えるやさしい育休プラン
- 「共働きだけど、どうやって育休を取ればいいの?」
- 「パパが育休を取ると職場に迷惑?」
そんな声にお応えして、夫婦で納得できる育休プランの立て方をご紹介します。
モデルケースを図で見てみよう
| 時期 | ママの予定 | パパの予定 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 出産前〜出産後 | 産前産後休業を取得 | — | ママは法律で休業が保障されている期間 |
| 出産後1か月以内 | 育休へ継続 | 育休を14日以上取得(出生後休業支援給付の対象に) | 出生後28日以内&14日以上がカギ |
| 賞与のある月 | 育休継続中 | 月初から月末まで育休を再取得(社会保険料免除の対象に) | ボーナス支給月を狙って育休を取得 |
パパの育休、ほんとに取れる?
- 会社は原則として育休を断れません(法律で守られています)
- ただしスムーズに取るためには、事前の相談・引き継ぎがとても大切
- 普段からチームを助けたり、情報共有をしっかりしておくと「安心して任せられる人」になります
夫婦のよくある不安と向き合うコツ
- パパ「キャリアに影響ある?」
→育休を取ったからといって評価が下がることは基本的にありません。
ただし、育休前にしっかり相談・引き継ぎをしておくことで、周囲からの信頼が高まり、むしろ評価がプラスになるケースもあります。



パパの育休は“キャリアダウン”じゃなくて、“信頼アップ”のチャンス。
事前準備こそ成功のカギだよ!育休を取ったからといって評価が下がることは基本的にありません。 ただし、育休前にしっかり相談・引き継ぎをしておくことで、周囲からの信頼が高まり、むしろ評価がプラスになるケースもあります。育休を取ったからといって評価が下がることは基本的にありません。 ただし、育休前にしっかり相談・引き継ぎをしておくことで、周囲からの信頼が高まり、むしろ評価がプラスになるケースもあります。
- ママ「パパの育休は、ほんとに役に立つの?」
→たとえば夜中の授乳のフォローや、寝不足の日のサポートなど、そばにいてくれるだけで気持ちに余裕が生まれます。 特に産後はホルモンバランスの変化などで、心が不安定になりやすい時期。パパの存在が、産後うつの予防や早期の気づきにもつながります。



「育休、取る・取らない」ではなく、「どう育てていく?」を話し合うと、お互い納得しやすくなります。 「育休、どうする?」ではなく、「どんなふうに一緒に育てていく?」という視点で話すと、より前向きに考えやすくなります 「育休、どうする?」じゃなくて「どんなふうに一緒に育てていく?」を軸に話すといいと思います。
まとめ:得する制度、知ってるか知らないかで差がつく
育休はただの「お休み」じゃありません。
制度を知って活用すれば、「家族の時間」と「家計の安心」の両方が手に入るチャンスです。
これからパパになる方も、今まさに育児中の方も、ぜひパートナーと一緒にこの記事を参考にして、
納得のいく育休プランを立ててみてくださいね。

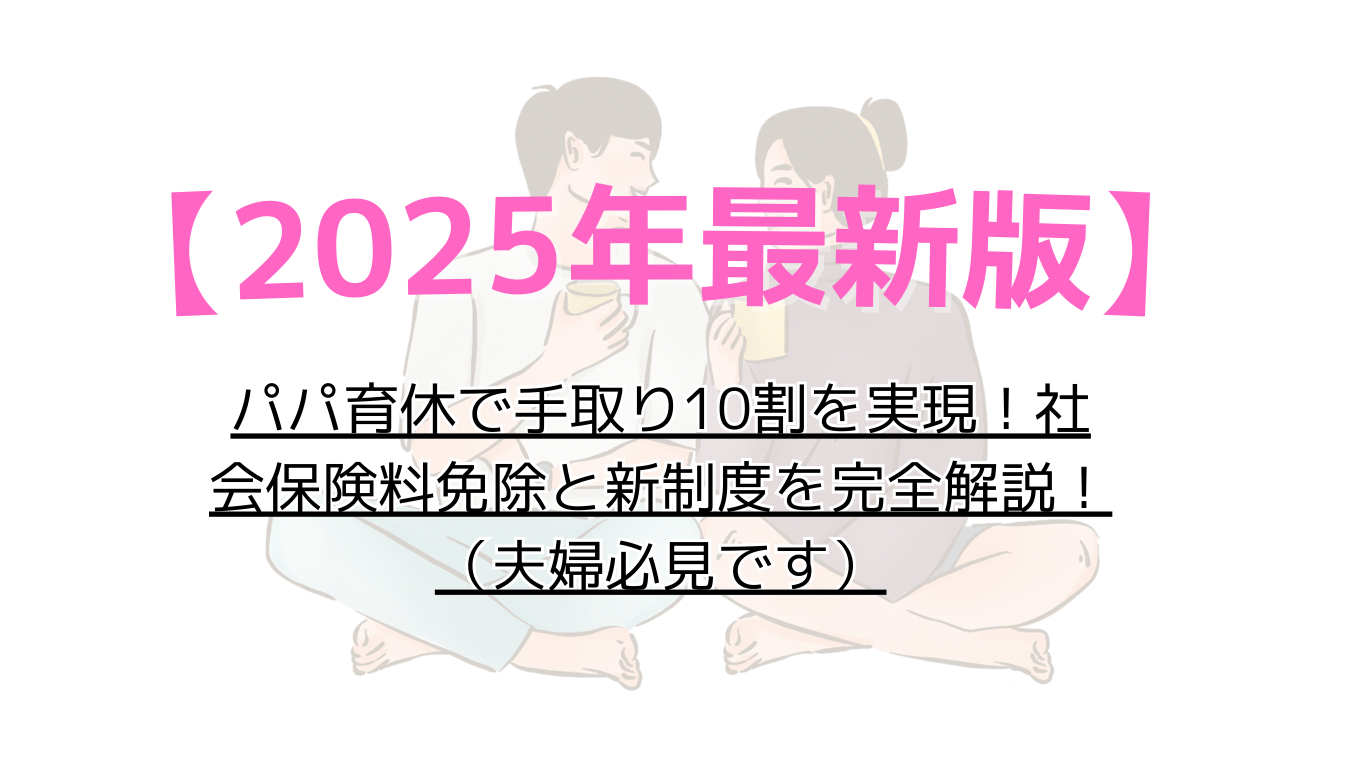
コメント